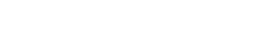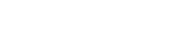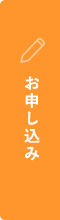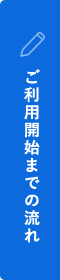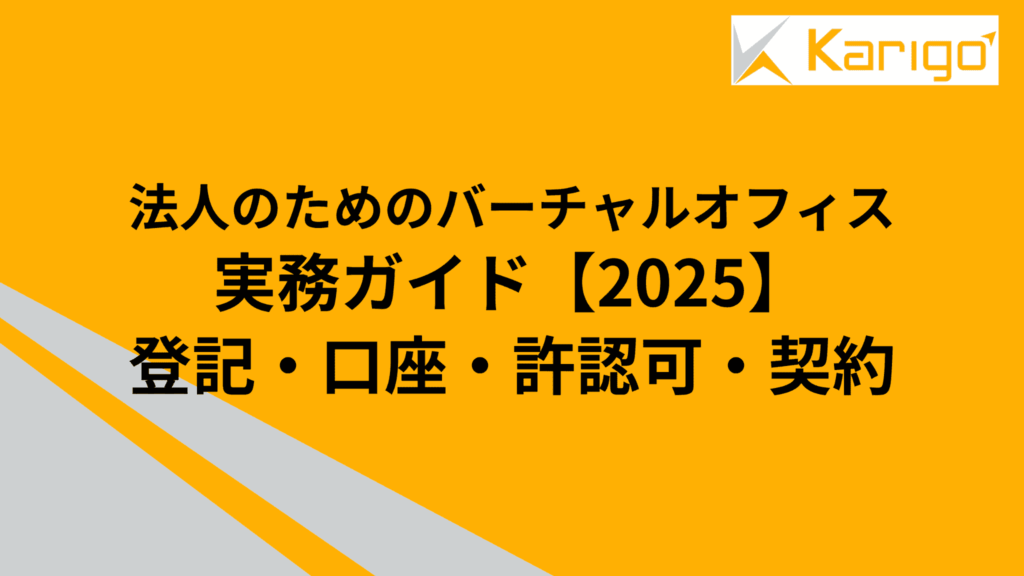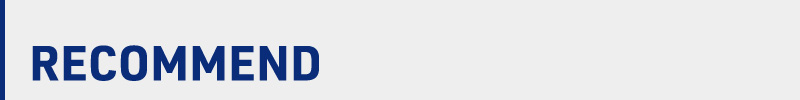会社の住所を低コストで確保しながら、信用と運用のしやすさも両立させたいと考える方が増えています。
バーチャルオフィスは、その解決策になり得ますが、法人で使う場合は「登記は本当にできるのか」「どの業種でもいいのか」「法人口座や取引先審査は通るのか」など、押さえるべき実務がいくつもあります。
本コラムでは、登記・許認可・口座・表示義務・選び方・導入フローまでを一気通貫で整理します。
必要なところで法令や公式ガイドラインを参照しながら、読み終えた時に“何をどう進めるか”がわかるようにお伝えします。
※詳しくはkarigoの店舗一覧を確認してください。
今回の記事を短く要約した動画はコチラ
法人でバーチャルオフィスを使う目的と適合範囲

法人での検討では、コスト削減だけでなく、信用や審査への対応が重要になります。
名刺やWebに表示する住所の印象、郵便物の確実な受け取り、会議室や来客対応の有無、電話番号の設計、そして将来的な本店移転や拠点追加のしやすさまで、バランスよく見ていく必要があります。
以下に、適切な使い分けや表示の考え方、既存法人が移転や拠点追加をするときの注意点を整理します。
本店所在地と支店/営業所登記の使い分け
設立時に本店をどこに置くかで、その後の税務署・年金事務所・労働局等の管轄が決まります。
本店は対外的な“顔”としての意味が大きいため、取引先や採用の観点で見栄えの良い住所を選ぶと説明がしやすくなります。
一方で、採用拠点や物流拠点など実務の重心が別にある場合は、支店や営業所として追設する方法が機能します。
いずれの形でも、同一住所で同一の商号(会社名)は登記できないため、申請前に重複の有無を確認しておくと安心です(商業登記法27条)。
会社情報の表示義務(特商法・会社法・Web表記)
ECやオンラインの役務提供を行う場合は、特定商取引法に基づく表示(事業者名・住所・電話番号・返品特約など)が求められます。
広告や申込ページで、消費者が容易に認識できる形での表示が必要とされます。住所にバーチャルオフィスを用いる場合も、正確に表記する前提は同じです。
既存法人の住所移転・拠点追加の注意点
本店移転や支店設置では、定款変更や登記、官公庁への届出が連動します。
移転先の建物に自社と同名の会社が既に登記されていると移転できないため、重複チェックは早めに行います。
移転後の請求書・Web・名刺・契約書・インボイス登録情報の表記更新も漏れなく行うと混乱を減らせます。
バーチャルオフィスでの法人登記と許認可の可否

結論からお伝えすると、バーチャルオフィスの住所でも法人の本店登記は可能です。
ただし、許認可や届出で「実態のある事務所」を要件にしている業種では、バーチャルオフィスだけでは要件を満たせない場合があります。
以下で、事前確認のポイントを具体的にご紹介します。
同一住所・同一商号の事前確認と回避策
「同一住所・同一商号」での登記はできません。商号や所在地が被らないか、申請前に確認しておくと手戻りを避けられます。
万一、同住所で同名の会社がある場合は、住所か商号のどちらかを見直す必要があります。
事務所(営業所)の設置要件が厳しい業種の判断軸
宅建業は標識掲示、帳簿備付け、独立スペースでの来客対応など、実店舗的な要件が重視されます。
時間貸しや共有区画では認められないケースがあるため、個室で常時占有できるかなど、自治体や団体の運用を確認しましょう。
有料職業紹介や労働者派遣でも、事務所の面積や体制に関する要件が示されることがあり、住所だけでは足りない場合があります。
古物商は「営業所」の実在性・現地確認が行われることがあり、事務所要件を満たす拠点の確保が前提になると考えたほうが安全です。
以下はオフィス要件が厳しい業種の一覧です。判断に迷う場合は担当官庁や警察署へ事前相談を行うのが確実です。
| 業種 |
| 人材派遣業(労働者派遣事業) |
| 有料職業紹介業 |
| 古物商 |
| 建設業 |
| 産業廃棄物処理業(収集運搬等) |
| 不動産業(宅地建物取引業) |
| 探偵業 |
| 金融商品取引業 |
| 風俗関連営業 |
| 一部の士業 |
管轄官庁への事前相談の進め方
疑問点があるときは、要件を定める省庁や労働局、所轄の警察署(古物商)に電話または窓口で確認します。
賃貸契約書や利用規約、占有証明、看板設置の可否、常駐・来客の運用など、判断材料になりそうな書面を持参すると話が早く進みます。
法人口座開設・取引先審査・インボイスで見られるポイント

口座や取引の審査では、住所そのものよりも「事業の実態」が見られます。
ホームページ、契約書・見積書、過去の取引実績、連絡体制、反社会的組織に対する対応、そして請求書の記載事項など、総合的に確認されます。
以下で、準備物と落ちやすいポイントを整理します。
事業実体の示し方(HP/契約書/納品実績/事業計画)
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認(KYC)があるため、業務内容・実質的支配者・取引目的などを説明できる資料を用意します。
事業サイトや会社案内、契約書・見積書、過去の取引実績、今後の事業計画をまとめると説得力が増します。
反社・AML対応/代表番号・連絡体制の整備
企業としての連絡手段(代表番号・メールアドレス・問い合わせフォーム)を整え、反社排除の姿勢を就業規則や基本合意書などに明記しておくと、先方の安心につながります。
KYC(顧客確認)の確認事項は全銀協の案内がわかりやすいので、事前に目を通してチェックリスト化しておくと対応がスムーズです。
否決されやすい理由と是正の実例
「事業の実態が見えない」「代表者不在で連絡がつかない」「請求書の記載が不完全」といった理由で見送りになることがあります。
適格請求書の登録番号(インボイス番号)の記載や、国税庁サイトで番号が検索可能であることを先方に示せるよう準備しておくと安心です。
選び方と料金の最適化(法人視点のチェックリスト)
-1024x559.jpg)
法人で選ぶ際は、「住所の価値」「郵便・荷物のSLA」「会議室・来客対応」「電話・秘書体制」「契約条件(最低利用期間・解約)」「証明書類の発行速度」などを、初期費用・月額・実費と合わせて総合評価することが大切です。
以下では、見落としやすい比較ポイントを押さえます。
住所価値・郵便/荷物SLA・会議室/来客対応
住所は地名の印象だけでなく、建物名・階数の表記まで確認します。郵便は「到着通知のタイミング」「転送頻度」「本人限定受取・書留への対応」を比較します。
会議室は採用面接や取引先審査など“対面の場”が必要な法人ほど重要です。
Karigoでは拠点により会議室を提供しており、予約方法やキャンセル規定は拠点ごとに案内しています。
電話番号・IVR・秘書代行の設計とコスト最適化
代表番号は、転送か秘書代行かで費用と品質が変わります。問い合わせの一次受けや不在時の取りこぼしを防ぐなら、秘書代行を検討すると安心です。
Karigoには電話転送や秘書代行のオプションがあり、固定電話番号の用意や時間外ガイダンスなどの運用も選べます。
契約条件(最低利用期間・解約・社名/拠点追加)の落とし穴
解約のしやすさ、拠点追加時の手数料、証明書発行のスピード、支払方法(カード・請求書)などは、運用面の満足度を左右します。
Karigoは店舗ごとに提供プラン・料金が異なり、契約中のプラン変更も可能です。候補住所ごとに“実務のしやすさ”を比較して決めると後悔が減ります。
導入フロー(既存法人/新設法人)と必要書類
と必要書類-1024x559.jpg)
導入の流れは、既存法人と新設法人で異なります。既存法人は移転や支店追加に伴う登記・届出が中心となり、新設法人は定款・設立登記・税務・社保・口座までの一連の手続きが続きます。
以下では、段取りを簡潔にまとめます。
既存法人:本店移転・支店追加・官公庁届出の段取り
バーチャルオフィスで既存法人の本店移転や支店追加を行う場合は、次の順番で進めると漏れが少なくなります。
1. 移転先のバーチャルオフィスを選定・契約し、同一住所・同一商号の有無を法務局で事前確認します。
2. 必要に応じて取締役会・株主総会の決議や定款変更を行い、本店移転(または支店設置)の登記申請を行います。
3. 税務署・都道府県税事務所・市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの異動届を提出します。
4. 最後に、会社サイトや名刺、請求書、適格請求書(インボイス)登録情報、取引基本契約、金融機関口座、クレジットカード、ECモールやSaaSなど各プラットフォームの住所変更、ならびに郵便転送届を順次更新します。
5. 銀行や主要取引先には早めに案内し、振込先や請求書の宛先変更を同時に進めるとトラブルを防げます。
新設法人:本店決定→定款→登記→税務/社保→口座開設
1. 本店所在地を決めてバーチャルオフィスを選定・契約します。住所要件や会議室の有無、郵便・電話の運用(SLA)を確認し、同一住所・同一商号の有無を法務局で事前に調べます。
2. 会社の基本事項を決めます。商号、事業目的、資本金、事業年度、役員体制を確定し、会社実印を用意します。
3. 定款を作成します。電子定款にすると印紙税を節約できます。株式会社は公証役場で認証が必要、合同会社は認証不要です。
4. 資本金を払い込みます。発起人等の口座へ払込み、払込証明書(通帳写し等)を整えます。
5. 設立登記を申請します。本店所在地を管轄する法務局へ、登記申請書・定款・払込証明・就任承諾書・印鑑届書などを提出します。完了後に履歴事項全部証明書と印鑑証明書を取得します。
6. 税務・社会保険等の届出を行います。税務署(法人設立届・青色申告申請・源泉所得税関係)、都道府県税/市区町村、年金事務所(新規適用届・資格取得届)、労基署・ハローワーク(労災・雇用保険)に順次届け出ます。
7. 法人口座開設の準備と申込みを行います。事業実体を示す資料(ウェブサイト、契約書・見積書、事業計画、実績資料)、バーチャルオフィスの契約書、必要に応じて許認可証を揃え、代表番号や問い合わせ体制も整えます。
8. インボイス制度の対応を進めます。課税事業者の選択と適格請求書発行事業者の登録を、開始時期から逆算して申請します。
9. 事業開始の周辺整備を行います。会社サイトや名刺、請求書(適格請求書対応)、特定商取引法の表示(該当時)、各種プラットフォームの登録、郵便転送設定、電話応対・来客ルールを整備します。
10. 関係先へ周知します。主要取引先や金融機関に、登記完了・新住所・振込先・請求書宛先などを早めに案内しましょう。
導入後30日で整える運用(転送設定・番号運用・来客ルール)
郵便の転送サイクルと通知先、代表番号の着信ルールや不在時フロー、会議室の利用ルールなどを、社内の運用ドキュメントとして固めます。
外部向けには、サイトの会社情報や特商法表示、Googleビジネスプロフィールの方針(登録可否の判断)も合わせて整えます。
法人運用の実務(郵便・電話・来客・情報管理)
-1024x559.jpg)
運用が整うと、郵便対応の速度や電話応対の品質が信用に直結します。
来客時の動線や受付方法、情報管理の手順まで、具体的に決めておくとトラブルを避けやすくなります。以下で実務の勘所をまとめます。
到着通知・転送頻度・保管期限の設計
郵便は「到着の検知→通知→転送→保管」の流れを決めます。重要書留や本人限定受取は別フローにして、担当者への連絡漏れを防ぎます。
Karigoでは郵便受取・転送を基本とした運用が可能で、拠点ごとに手続きや費用が異なるため、契約時に確認しておくと安心です。
代表番号/内線・転送・受付対応のルール化
営業時間外のガイダンス、一次応対のスクリプト、メモの共有方法を事前に決めておくと、問い合わせの取りこぼしが減ります。
Karigoの電話オプション(転送・秘書代行)は、固定番号の用意や時間外アナウンスなどの設計に対応しています。
移転時のダメージ最小化(住所変更登記・周知・SLA再設計)
移転が必要になった場合は、登記・官公庁届出・GoogleやSNS・取引先への周知を一気通貫で行います。
郵便・電話・会議室のSLA(通知・転送・予約可用性)も見直し、新住所での運用を早期に安定させます。
まとめ|「法人の信用を損なわない」バーチャルオフィス活用の要点
今回の記事では、法人がバーチャルオフィスを活用する際の登記可否、許認可や口座審査への対応、選び方と運用の勘所をご紹介しました。
・同一住所・同一商号の有無を確認し、事務所の設置要件(専用区画・独立性・来客対応など)を満たす必要があります。
・KYCに耐える事業実体の資料と連絡体制を整えます。
・住所価値・郵便/電話/会議室・契約条件を総合評価します。
以上のポイントを踏まえ、低コストと信用を両立できる住所戦略を設計し、信頼できる事業者とともに着実に実行してください。
※詳しくはkarigoの店舗一覧を確認してください。