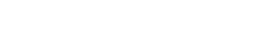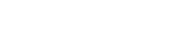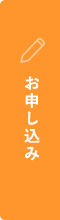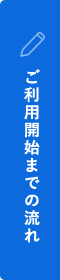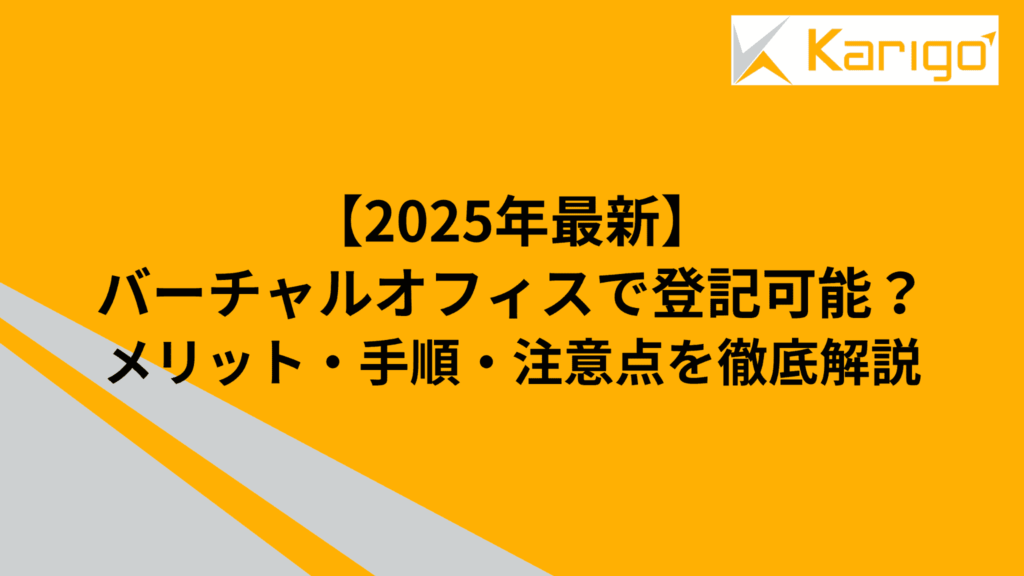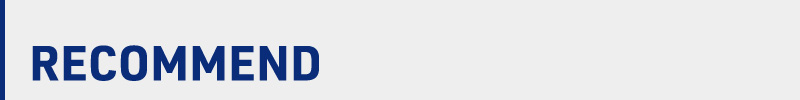起業や副業を始める際、「自宅住所を公開したくない」「初期費用を抑えたい」と考える方は多いでしょう。
そんな時に注目されるのがバーチャルオフィスです。しかし、「バーチャルオフィスで本当に法人登記ができるのか?」「銀行口座は開設できるのか?」といった不安を抱える方も少なくありません。
本記事では、バーチャルオフィスでの登記可能性について法的根拠から実務まで、メリット・デメリット、具体的な手順、信頼できる事業者の選び方まで、2025年最新情報をもとに徹底解説します。
※詳しくはkarigoの店舗一覧を確認してください。
今回の記事を短く要約した動画はコチラ
バーチャルオフィスとは?法人登記に使える基礎知識
 バーチャルオフィスで法人登記を検討する前に、まず「どのようなサービスなのか」を正しく理解しておきましょう。
バーチャルオフィスで法人登記を検討する前に、まず「どのようなサービスなのか」を正しく理解しておきましょう。
バーチャルオフィスとは、実際の執務スペースを持たずに事業運営に必要な拠点機能(住所利用・郵便物受取など)を提供する仕組みです。
サービスによっては、電話番号や会議室利用などのオプション機能を追加できる場合もあります。
法人登記に利用できる住所を持ちながら、コストを抑えて信用力を確保できる点が、個人事業主や起業家に選ばれている理由です。
バーチャルオフィスの定義と基本サービス
バーチャルオフィスとは、実際の執務スペースを持たずに事業を運営できるサービスです。
提供される主な機能は「登記可能な住所」「郵便物の受取・転送」「電話番号・FAX番号の取得」「会議室利用」などです。
自宅住所を公開せずに法人登記ができることが最大の特徴であり、特に個人事業主やスタートアップに支持されています。
プライバシーを守りながら事業をスタートできる点が評価されています。
レンタルオフィス・コワーキングスペースとの違い
レンタルオフィスやコワーキングスペースは「作業する物理的な場所」を提供します。
一方、バーチャルオフィスは住所や連絡機能に特化し、作業スペースを持たないのが大きな違いです。
料金は圧倒的に安価で、最安値では月額数100円台から、実用的なサービスでも月額3,000円〜10,000円程度が相場です。
レンタルオフィスが1人用個室でも月額3万円以上かかるのに対し、年間20万円以上のコスト削減が可能です。
個人事業主・スタートアップに選ばれる理由
自宅住所を公開せずに法人登記でき、都心一等地の住所を名刺やWebサイトに記載できる点が魅力です。
特に女性起業家にとっては、自宅住所の公開によるプライバシーリスクやセキュリティ上の懸念を回避できるため、安心して事業を始められます。
また、オフィス賃料を大幅に削減できるため、資金に余裕のない創業期でも安心して法人化できます。
副業で起業する人や、フルリモートで事業を進めるスタートアップが導入しやすい理由もここにあります。
バーチャルオフィスで法人登記は可能?法的根拠と条件
 「バーチャルオフィスで本当に法人登記ができるのか?」これは、起業を検討するほぼすべての方が抱く疑問です。
「バーチャルオフィスで本当に法人登記ができるのか?」これは、起業を検討するほぼすべての方が抱く疑問です。
結論から言えば、バーチャルオフィスでの法人登記は、商業登記法に基づいて認められています。ただし、いくつかの条件があります。
実際に法務局でも、バーチャルオフィスの住所を利用した登記申請が日常的に受理されています。ここでは法的根拠と実務上押さえるべき条件を詳しく解説します。
商業登記法における本店所在地の規定
法人を設立する際には、本店所在地(会社の住所)を登記簿に記載する必要があります。
この住所は、事業の拠点として機能し、郵便物や法的書類を確実に受け取れる場所であれば問題ありません。
重要なのは、本店が必ずしも「物理的な事務所」である必要はないという点です。
一般的な登記実務上は、「会社が事業運営の拠点として利用する住所」であれば本店所在地として認められます。
実際に代表者が常駐している必要はなく、郵便物が届き、法的書類を受け取れる場所であれば要件を満たします。
そのため、バーチャルオフィスの住所を本店所在地として登記することも可能です。
バーチャルオフィスで登記が認められる理由
バーチャルオフィスは、事業の拠点として住所を利用できる権利を契約によって提供するサービスです。
物理的な賃貸借契約ではありませんが、住所利用の権限が正式に認められる仕組みが整っているため、登記にも活用できます。
Karigoでは、Web上で契約手続きが完結し、契約書面は発行されませんが、登記や各種届出に利用できる「利用証明書」の発行が可能です。
これにより、法務局での登記や銀行などへの住所証明としても安心して利用できます。
契約内容・住所表記・本人確認などの実務条件
登記がスムーズに行えるかどうかは、事業者の運用体制や契約内容によって異なります。以下のポイントを確認しておきましょう。
確認すべき3つのポイント
1.登記利用が明示的に認められているか
Karigoのように、公式サイト上で「法人登記・開業届対応可」と明記されている事業者を選ぶことが大切です。
2.住所表記の明確さ
登記簿に記載する住所は、「東京都渋谷区○○1-2-3 ○○ビル4階」など、建物名・階数まで正確に表記できるか確認しましょう。
3.本人確認(eKYC)と審査の厳格性
Karigoではオンライン本人確認(eKYC)を導入し、身分証の照合や反社チェックを実施しています。
このような厳格な審査体制がある事業者を選ぶことで、銀行口座開設や取引先審査の信頼性も高められます。
これらの条件を満たすバーチャルオフィスを選ぶことで、法務局での登記受理や金融機関での審査もスムーズに進みやすくなります。
バーチャルオフィスで登記できない業種一覧
 バーチャルオフィスは多くの業種で利用可能ですが、一部の業種では法人登記が認められません。
バーチャルオフィスは多くの業種で利用可能ですが、一部の業種では法人登記が認められません。
これは、許認可の取得要件として「事務所の実態」が求められるためです。起業前に必ず自分の事業がバーチャルオフィスで登記可能かを確認しましょう。
許認可が必要な業種の制限
許認可事業の多くは、監督官庁が「事業を行うための物理的な事務所」の存在を確認します。
この確認が行えないバーチャルオフィスでは、許認可が下りず、結果として事業を開始できません。
特に、顧客や求職者の個人情報を扱う業種、公共性の高い業種、安全管理が求められる業種では、実態のある事務所が必須となります。
事務所の実態が求められる業種リスト
以下の業種では、バーチャルオフィスでの法人登記が認められないか、取得できない可能性があります。
人材派遣業・職業紹介業
労働者派遣法により、派遣元の事務所には一定の面積(概ね20㎡以上)と専用スペースが必要です。職業紹介業も同様に、職業安定法で事務所要件が定められています。
建設業
建設業許可を取得するには、営業所に事務スペース、応接スペース、工事経歴書などの保管場所が必要です。バーチャルオフィスでは要件を満たせません。
不動産業
宅地建物取引業の免許取得には、専任の宅地建物取引士が常駐できる事務所が必要です。また、物件情報の掲示スペースや応接スペースも求められます。
古物商・探偵業
古物営業法では、盗品の流通を防ぐため、実態のある営業所が必須です。探偵業も探偵業法により、事務所の実態確認が行われます。
士業(弁護士・税理士等)
弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業は、各法律により事務所の設置が義務付けられています。顧客との面談スペースや書類保管場所が必要です。
業種別の登記可否判断基準
登記可能な業種
・IT・Web関連事業
・コンサルティング業
・デザイン・クリエイティブ業
・ECサイト運営
・マーケティング・広告代理店
・フリーランス・個人事業
事前確認が必要な業種
・飲食業(営業許可は別途実店舗が必要)
・輸入業(税関への届出に注意)
・介護・福祉事業(指定申請の要件確認が必要)
事業を始める前に、所轄の役所や専門家(行政書士・司法書士)に相談することを強くおすすめします。
バーチャルオフィス登記のメリットとデメリット
 登記可能なバーチャルオフィスを利用することで、多くのメリットを享受できますが、一方でデメリットも存在します。
登記可能なバーチャルオフィスを利用することで、多くのメリットを享受できますが、一方でデメリットも存在します。
メリットとデメリットの両面を理解することで、判断を誤らないようにしましょう。
メリット①初期費用・ランニングコストを大幅削減
賃貸オフィスを借りる場合、敷金・礼金・仲介手数料だけで家賃の6ヶ月分程度かかります。月額家賃が10万円なら初期費用だけで60万円です。
一方、バーチャルオフィスなら初期費用は5,000円〜3万円程度、月額料金も1,000円〜5,000円で済みます。年間のコスト差は50万円以上になることも珍しくありません。
創業期の資金を商品開発やマーケティングに回せるため、事業成長のスピードを加速できます。
メリット②自宅住所を公開せずプライバシーを保護
法人登記した住所は、誰でも法務局で閲覧可能な公開情報です。自宅で登記すると、住所が第三者に知られるリスクがあります。
特に女性起業家や、家族と同居している方にとって、自宅住所の公開は大きなセキュリティリスクです。
バーチャルオフィスを利用すれば、プライベートな住所を守りながら事業活動ができます。
メリット③一等地の住所でビジネスの信頼性向上
銀座、渋谷、新宿、丸の内といった一等地の住所を名刺やWebサイトに記載できることは、取引先への安心感や信頼感につながりやすい要素です。
同じサービス内容であっても、「東京都渋谷区」と「地方の住宅街」など所在地の印象によって、無意識的に評価が変わる場合もあります。
特にBtoB事業では、住所のブランド力が第一印象を左右し、商談時の信頼形成にプラスに働く傾向があります。
メリット④即日利用開始でスピーディーな起業が可能
契約したその日から住所を利用できるサービスもあり、スピーディーな法人設立を可能にします。
賃貸オフィスの場合、物件探しから契約、内装工事まで数ヶ月かかることもありますが、バーチャルオフィスなら最短即日で事業をスタート可能です。
また、郵便転送や電話代行、会議室利用など、事業運営に役立つ機能がまとめて利用できる点も魅力です。
デメリット①銀行口座開設や融資審査が厳しくなる可能性

金融機関や取引先によっては「バーチャルオフィス=実態がない」とみなされ、口座開設や融資が難しくなる場合があります。
特にメガバンクでは、バーチャルオフィスでの登記だけでは口座開設を断られるケースも報告されています。
対策としては、事業計画書、Webサイト、取引先との契約書など、事業実態を証明する書類を整備しておくことが重要です。
また、口座開設実績が豊富なバーチャルオフィスを選ぶことで、審査通過率を高められます。
デメリット②同一住所に複数の法人が登記されるリスク
バーチャルオフィスは1つの住所を複数の企業が共有するため、同じ住所に多数の企業が登記されていることもあります。
取引先が登記情報を確認した際、同住所に複数社が登記されていることに気づく場合があります。
近年ではバーチャルオフィスの認知度が高まり、IT・コンサル・EC事業などリモート中心のビジネスでは一般的な選択肢として受け入れられていますが、業種や取引先によっては説明が必要になるケースもあります。
対策としては、厳格な審査基準を設けているバーチャルオフィスを選ぶこと、自社のWebサイトで事業内容を詳しく公開することが有効です。
これにより、事業実態を明確に示し、取引先からの信頼を確保できます。
デメリット③バーチャルオフィス事業者の倒産リスク
事業者が倒産した場合、登記住所を失うリスクがあります。住所変更の登記には、管轄内で3万円、管轄外で6万円の登録免許税がかかり、さらに各所への届出も必要です。
創業20年以上、利用者数が10,000社以上といった実績のある事業者を選ぶことで、このリスクを最小限に抑えられます。
Karigoは創業20年以上、延べ70,000社を超える企業様にご利用いただいており、全国61拠点を展開する業界随一の老舗企業です。
長年の運営実績と全国規模のネットワークにより、安定したサービス提供が可能で、安心して法人登記を進めることができます。
バーチャルオフィスで法人登記する手順

バーチャルオフィスを利用して法人登記を行う流れは、大きく5ステップに分かれます。実務的に押さえておくべき注意点を解説します。
STEP1:バーチャルオフィスの選定と契約
最初のステップは「登記可能」と明記されたバーチャルオフィスを契約することです。契約前に以下のチェックリストで確認しましょう。
【チェックリスト】バーチャルオフィス選定時の確認項目
□「法人登記可能」と明記されているか
□法務局での登記受理実績があるか
□銀行口座開設サポート・実績の有無
□郵便物転送の頻度(週1回/月1回など)
□反社チェック・本人確認の厳格性
□契約期間の縛り(最低利用期間)
□初期費用・月額費用の明瞭性
□会議室やワークスペースの有無
□電話転送・秘書代行サービスの内容
□運営会社の実績・信頼性
選定を誤ると、登記後に口座が開けない、郵便物が届かないなど大きなトラブルにつながります。複数のサービスを比較し、口コミや実績を確認してから契約しましょう。
STEP2:定款の作成と住所記載
法人設立には定款が必須で、そこに本店所在地としてバーチャルオフィス住所を記載します。定款には2つの記載方法があります。
定款への住所記載方法
1.最小行政区画まで記載(推奨)
例:「東京都渋谷区」
メリット:将来の住所変更時に定款変更が不要
2.具体的な住所まで記載
例:「東京都渋谷区道玄坂○丁目○番○号」
メリット:より明確だが、移転時に定款変更が必要
電子定款を利用すれば印紙代4万円を節約できます。freee会社設立やマネーフォワード会社設立などのオンラインサービスを利用すれば、専門知識がなくても簡単に作成可能です。
定款の「本店所在地」欄には、市区町村までの記載でよい場合と、丁目・番地・部屋番号まで必要な場合があるため、専門家や法務局で確認しておくと安心です。
STEP3:類似商号の確認方法
同一住所に同じ商号(会社名)が既に登記されている場合、登記ができません。バーチャルオフィスは複数社が同じ住所を使うため、事前確認が特に重要です。
確認方法
1.法務局の窓口で確認
管轄の法務局で「商号調査」を依頼すれば無料で確認できます。
2.登記情報提供サービス
オンラインで有料(1件331円)で確認可能
一般財団法人民事法務協会>登記情報提供サービス
3.バーチャルオフィス事業者に問い合わせ
多くの事業者が類似商号の有無を教えてくれます。
類似商号が見つかった場合は、社名を変更するか、別のバーチャルオフィスを検討する必要があります。
STEP4:法務局への登記申請
定款を公証役場で認証後、法務局へ登記申請します。登記申請には以下の書類が必要です。
必要書類
・登記申請書
・定款
・発起人の決定書
・設立時取締役の就任承諾書
・印鑑証明書
・資本金の払込証明書
・印鑑届出書
登記完了には通常1〜2週間かかります。オンライン申請(法人設立ワンストップサービス)を利用すれば、自宅からでも申請可能です。
登録免許税は「資本金額×0.7%」が基本ですが、最低税額が定められています。株式会社は15万円以上、合同会社は6万円以上が必要です。
STEP5:登記完了後の各種届出
登記しただけでは会社運営は始まりません。設立後に必要な届出を期限内に完了させることが重要です。
必須の届出
1.税務署への届出(設立から2ヶ月以内)
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
2.都道府県税事務所・市町村役場(設立から1ヶ月以内)
・法人設立届出書
3.年金事務所(従業員雇用の場合、速やかに)
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・被保険者資格取得届
4.労働基準監督署・ハローワーク(従業員雇用の場合)
・労働保険関係成立届
・雇用保険適用事業所設置届
期限を過ぎると罰則や不利益が生じる場合があるため、司法書士や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
銀行口座開設・融資・信用面への影響

バーチャルオフィスで登記した後、多くの経営者が直面するのが銀行口座開設や融資審査の壁です。ここを突破できるかどうかが、事業スタートの加速に直結します。
メガバンクとネット銀行の審査難易度
メガバンク(三菱UFJ・三井住友・みずほ)の特徴
メガバンクは「事業の実体」を特に重視します。バーチャルオフィスのみの登記では口座開設が難しいことも少なくありません。
面談が必須となり、事業計画や事業実態の詳細な説明を求められます。
審査には2週間〜1ヶ月程度かかり、書類不備があるとさらに時間がかかります。ただし、開設できれば対外的な信用力は非常に高くなります。
ネット銀行(GMOあおぞら・住信SBI・楽天銀行など)の特徴
ネット銀行は比較的柔軟で、事業計画やWebサイトを重視する傾向があります。オンライン完結で審査が進むため、スピーディーに口座開設できる場合が多いです。
特にGMOあおぞらネット銀行や住信SBIネット銀行は、バーチャルオフィス利用者の口座開設実績が豊富で、審査通過率が高いと報告されています。振込手数料も安価で、スタートアップに適しています。
口座開設に必要な書類と事業実態を示す準備
銀行口座開設には、登記簿謄本や印鑑証明書といった基本書類に加え、事業実態を証明する資料が求められます。
基本書類
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・会社の印鑑証明書
・代表者の身分証明書
・代表者の印鑑証明書
事業実態を示す書類(重要)
・事業計画書(3〜5年分)
・会社のWebサイト(必須)
・会社案内・パンフレット
・取引先との契約書・発注書
・オフィスの賃貸契約書(バーチャルオフィスの利用契約書)
・代表者の職務経歴書
・資本金の出所を示す資料
事業の実態を示す証拠を提出できると審査が通りやすくなります。特に初年度は売上証明がないため、「これから事業が動き出す証拠」を示すことが重要です。
Webサイトは必須です。会社概要、事業内容、代表者プロフィール、問い合わせフォームを最低限整備しましょう。
口座開設や融資を通過しやすくするポイント
口座開設のポイント
1.事前に銀行の法人営業担当へ相談
窓口やコールセンターではなく、法人営業担当に直接相談すると、必要書類や審査基準を教えてもらえます。
2.登記先のバーチャルオフィスの実績確認
Karigoのように「銀行口座開設実績あり」と公表している事業者を選ぶと、安心して準備を進められるでしょう。
実績があること自体が審査結果を左右するわけではありませんが、開設に向けた書類準備や流れを理解しやすいという利点があります。
3.資本金は100万円以上が望ましい
最低資本金制度は廃止されましたが、資本金が少なすぎると信用力が低いと判断される場合があります。
4.代表者の信用情報に問題がないか確認
過去の金融事故(自己破産、延滞など)があると審査に影響します。
自宅登記やレンタルオフィスとの比較

登記先の選択肢は「自宅」「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」の3つです。
それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自社の事業に最適な方法を選びましょう。
自宅登記のメリット・デメリット
メリット:
・コストゼロで登記可能
・事務所契約の手間がない
・実際に作業する場所と登記住所が一致
デメリット:
・住所が公開情報となりプライバシーリスクが高い
・賃貸物件では契約違反となる場合がある(大家の承諾が必要)
・自宅住所では信用力が低いと判断される場合がある
・家族との同居で、郵便物や来客対応に支障が出る可能性
特に女性起業家、副業で法人化する会社員、家族と同居している方にとって、自宅住所の公開は大きなリスクです。
また、住宅街の住所よりも、ビジネス街の住所の方が取引先からの信用を得やすい傾向があります。
バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違い
バーチャルオフィスの特徴:
・月額1,000円〜5,000円程度
・住所・郵便受取・電話転送機能のみ
・作業スペースは基本的になし(会議室は別途レンタル可能)
・敷金礼金不要で初期費用が安い
・プライバシー保護とコスト削減に最適
レンタルオフィスの特徴:
・月額3万円〜15万円程度
・個室または共有の作業スペースあり
・デスク、椅子、Wi-Fi、複合機などが完備
・来客対応や打ち合わせに対応可能
・許認可が必要な業種でも利用できる場合が多い
選び方の基準
| 項目 | バーチャルオフィス | レンタルオフィス |
| 作業場所の必要性 | 不要(在宅・リモート中心) | 必要 |
| 来客頻度 | 少ない | 多い |
| 従業員数 | 0〜2名程度 | 3名以上 |
| 初期コスト | 重視する | ある程度許容できる |
| 許認可業種 | 該当しない | 該当する |
将来の事業計画に応じた選び方
創業期はバーチャルオフィスで十分でも、従業員採用や来客対応が増えるとレンタルオフィスや自社オフィスへ移行するのが自然です。
実際にKarigoをご利用いただいた企業の中には、事業が軌道に乗り会社規模が拡大したことで、バーチャルオフィスを卒業して自社オフィスやレンタルオフィスへステップアップされた成功事例が複数あります。
バーチャルオフィスは起業の最初のステップとして、最適な選択肢といえるでしょう。
事業ステージ別の推奨:
創業〜1年目:バーチャルオフィス
・コストを最小限に抑え、商品開発やマーケティングに資金を集中
・顧客獲得と事業モデルの検証に専念
2〜3年目:バーチャルオフィス継続orレンタルオフィス
・従業員採用や取引先との対面機会が増えたらレンタルオフィスへ
・引き続きリモート中心ならバーチャルオフィスで問題なし
4年目以降:自社オフィスorレンタルオフィス
・安定した売上が確保できたら自社オフィスも検討
・ブランディングや採用強化のため一等地のオフィスへ投資
重要なのは、「今の事業ステージに最適な選択をする」ことです。無理に高額なオフィスを借りる必要はありません。
登記住所変更の実務と費用
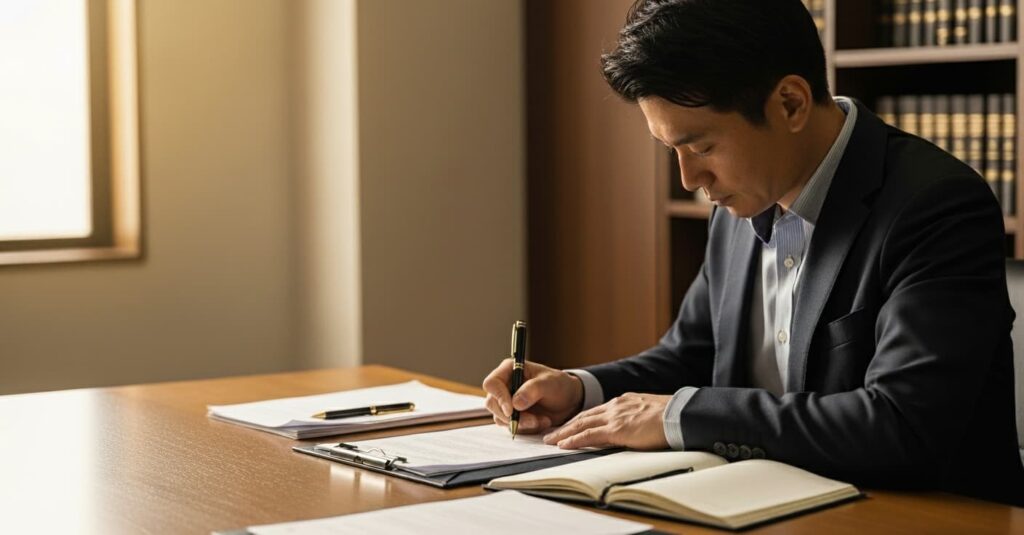
会社の成長や拠点移転に伴い、登記上の本店所在地(登記住所)を変更するケースは珍しくありません。
バーチャルオフィスから別拠点への移転やレンタルオフィス・自社オフィスへの変更など、本店移転には一定のコストと事務手続きが伴います。
ここでは、実務上のパターン別費用目安と関連の注意点を整理します。
本店移転登記の流れと「管轄内/管轄外」移転の違い
本店移転登記には、大きく「管轄内移転」と「管轄外移転」の2種類があります。手続きの複雑さ・添付書類・登録免許税の負担などで差が生じます。
管轄内移転(同一法務局管轄内)
例:区内から同じ区内、または市内での移転。
主な流れ:取締役会決議 → 新オフィス契約 → 本店移転登記申請(移転日から2週間以内) → 登録免許税 3万円を納付。
管轄外移転(異なる法務局管轄へ移転)
例:区をまたいだ移転、市をまたいだ移転など。
主な流れ:株主総会で定款変更決議 → 取締役会決議 → 旧所在地および新所在地双方の登記申請 → 登録免許税 6万円(3万円×2)納付。
移転後2週間以内の登記申請が一般的な義務とされています。遅延は法務局手続きに支障を来す可能性があります。
登録免許税・定款変更・司法書士報酬など費用目安
登録免許税
管轄内移転:3万円
管轄外移転:6万円(旧所在地3万円+新所在地3万円)
定款変更の要否
定款の本店所在地の記載方法によって、変更の要否が決まります。
「東京都渋谷区」のみ記載:区内の移転なら変更不要
「東京都渋谷区道玄坂○丁目○番○号」まで記載:番地が変われば変更必要
定款変更が必要な場合は、株主総会での特別決議(議決権の2/3以上の賛成)が必要です。
司法書士への依頼費用
自分で手続きすることも可能ですが、司法書士に依頼する場合の相場は以下の通りです。
管轄内移転:3〜5万円
管轄外移転:5〜8万円
総費用は、管轄内で6万円〜8万円、管轄外で11万円〜14万円程度が目安です。
移転時に必要な関連届出と注意点
法務局での変更登記だけでなく、以下の届出も必要です。期限内に届出を行わないと、罰則や不利益が生じる場合があります。
必須の届出先
☑税務署(移転後速やかに)
本店所在地移転の異動届出、給与支払事務所等移転届出
☑都道府県税事務所・市町村役場(移転後速やかに)
異動届出書
☑年金事務所(移転後5日以内)
適用事業所所在地変更届
☑労働基準監督署・ハローワーク(従業員がいる場合)
所在地・名称変更届
☑銀行・取引先・郵便局・契約先
住所変更通知
これらを漏れなくスケジュール管理し、チェックリストを活用することを強く推奨します。
個人事業主・EC事業者のバーチャルオフィス活用法
 バーチャルオフィスは法人だけでなく、個人事業主・フリーランス・ネットショップ運営者にとっても、欠かせない存在になりつつあります。
バーチャルオフィスは法人だけでなく、個人事業主・フリーランス・ネットショップ運営者にとっても、欠かせない存在になりつつあります。
開業届や特定商取引法の住所表示、郵便物対応まで一貫して使えるため、「自宅住所を公開せずに事業を行いたい」人に最適です。
ここでは、個人事業主の法的活用方法からEC運営における信頼性向上まで、最新の実務ポイントを詳しく解説します。
個人事業主の開業届・屋号利用で自宅住所を公開せずに事業運営する方法
個人事業主が開業届を提出する際、納税地として「住所地」「居所地」「事業所」のいずれかを選択できます。
バーチャルオフィスはこのうちの「事業所」として登録でき、税務署にも正式に認められています。
開業届の書き方例
☑納税地:自宅住所(または住所地)
☑事業所:バーチャルオフィスの住所
☑屋号:任意(例:「株式会社サンプル」→「サンプルデザイン」など)
この形式で提出すれば、Webサイトや名刺にはバーチャルオフィスの住所を掲載でき、自宅住所を公開する必要がありません。特に、女性起業家や副業ワーカーに人気の方法です。
注意点
・確定申告書や青色申告承認申請書は納税地の税務署に提出。
・事業所として届出ても納税地は自宅住所のまま。
・郵便物を屋号+氏名で受け取れるバーチャルオフィスを選ぶと便利。
Karigoのように「屋号郵便対応可」「登記・開業届対応可」と明記している事業者を選ぶと安心です。
特定商取引法に基づく住所表示をバーチャルオフィスで安全に行う方法
ECサイトやネットショップを運営する場合、特定商取引法により以下の情報を表示する義務があります。
必須表示項目
事業者の氏名(法人の場合は名称)
住所
電話番号
メールアドレス
自宅住所を記載したくない場合、バーチャルオフィスの住所を利用すれば、法律で定められた要件を満たしつつプライバシーを守れます。
実際の記載例
運営者:株式会社○○(または個人事業主氏名)
所在地:〒150-0043東京都渋谷区
電話番号:XX-XXXX-XXXX
メールアドレス:info@example.com
ただし、消費者からの問い合わせに対応できることが前提です。郵便物の転送や電話転送サービスを利用し、確実に連絡が取れる体制を整えましょう。
ECサイト運営で信頼性を高める住所選びと郵便・返品対応のポイント
EC運営で最も重要なのは、「このショップは信頼できるか」という印象です。
都心の一等地住所を使用するだけで、顧客に「しっかりした企業」という信頼感を与えることができます。
信頼性を高めるポイント
☑東京都渋谷区や大阪市中央区などビジネス街の住所を表示
☑顧客対応窓口を明記(電話・メール・チャットなど)
これにより、購入前の不安「本当に届くのか?」を解消し、コンバージョン率の向上にもつながります。
郵便物・返品対応を円滑にする機能
☑郵便物の到着通知(写真付き)
☑週次・月次の定期転送
☑即日転送オプション
☑宅配便・返品商品の受取対応
Karigoでは全国61拠点で郵便物・宅配便の受取・転送に対応しており、一部の主要都市拠点では即日転送オプションも利用できます。
特に返品対応を行うショップでは、顧客からの荷物を確実に受け取れる体制が信頼に直結します。
バーチャルオフィス選びの重要ポイント
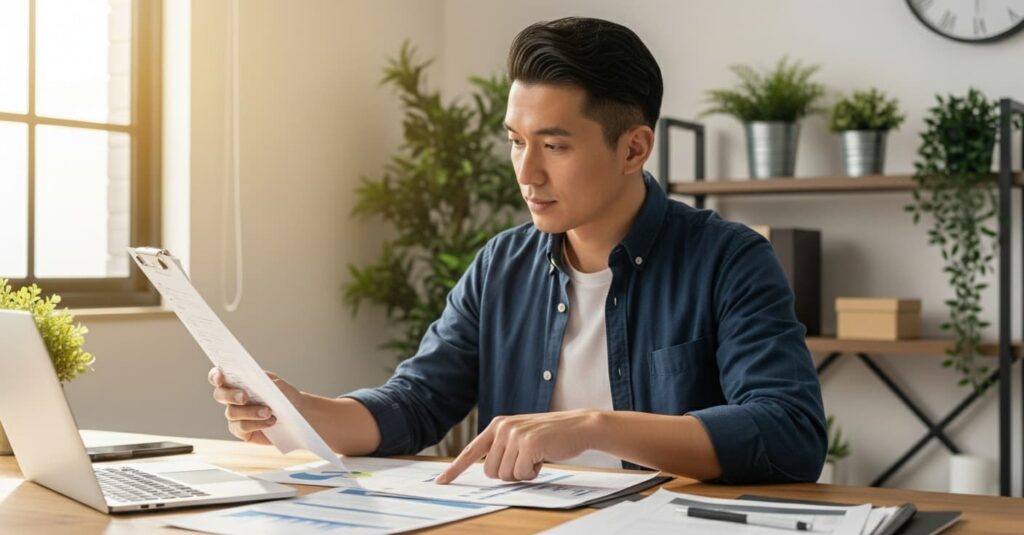 登記や銀行口座開設で失敗しないためには、信頼できるバーチャルオフィス事業者の選び方を理解することが重要です。
登記や銀行口座開設で失敗しないためには、信頼できるバーチャルオフィス事業者の選び方を理解することが重要です。
以下のポイントをチェックして、安心して登記できる拠点を選びましょう。
運営事業者の信頼性と審査基準
バーチャルオフィス選びで最も重要なのが「運営実績」と「審査の厳格さ」です。
信頼できる事業者の条件
☑創業10年以上、利用者数1万社以上
☑全国展開しており複数拠点を運営
☑本人確認や反社チェックを徹底
審査が甘い事業者は不正利用リスクが高く、同住所登記の他社の影響で銀行口座開設が不利になる場合もあります。
Karigoは創業20年以上・延べ70,000社超の利用実績を持ち、厳格な審査体制で安心して利用できる業界最大級の事業者です。
立地・住所のブランド力
登記住所は会社の「信用」を左右します。ビジネス街の住所は信頼性アップの重要要素です。
人気のエリア例
東京:銀座・丸の内・渋谷・新宿
大阪:梅田・本町
名古屋:栄・名駅
福岡:天神・博多
特にBtoBビジネスでは住所の印象が商談の第一印象を左右します。Karigoは全国61拠点を展開し、一等地の住所で登記できるバーチャルオフィスを提供しています。
郵便物転送・会議室・電話対応などのオプション
住所だけでなく、事業運営を支えるサービス機能も重要です。
主な確認ポイント
☑郵便転送(週1・月1・即日対応など)
☑会議室の有無・料金・予約方法
☑専用電話番号や秘書代行の有無
これらのオプションは事業スタイルに直結します。取引先対応が多い場合は会議室、在宅業務中心なら電話転送機能を重視しましょう。
銀行口座開設の実績・サポート体制
バーチャルオフィスでの登記後に問題になりやすいのが銀行口座開設の可否です。実績やサポートがある事業者を選ぶと安心です。
確認ポイント
☑銀行口座開設実績(提携先・成功率)
☑必要書類のサポート有無
☑開設支援サービスの有無
Karigoでは銀行口座開設実績が豊富で、利用者向けのアドバイスやサポート体制も整っています。
料金体系の透明性とコストパフォーマンス
料金が不明瞭なサービスは避けましょう。初期費用・月額費用・オプション料金が明確で、長期利用を見据えても負担が少ないか確認が必要です。
料金比較のポイント
| 項目 | 確認内容 |
| 初期費用 | 入会金、保証金、事務手数料 |
| 月額基本料金 | 最安プランの料金 |
| 郵便転送料 | 転送1回あたりの料金、実費負担の有無 |
| 会議室利用料 | 1時間あたりの料金 |
| 電話転送料 | 月額基本料金、転送料 |
| 契約期間 | 最低利用期間、解約時の違約金 |
料金の明瞭さは信頼性と直結します。初期費用・月額料金・郵便物送料・転送費用・会議室利用料などを比較しましょう。
| 価格帯の目安 | 金額 |
| 格安 | 月額660〜1,500円(郵便物転送別) |
| 標準 | 月額3,000〜6,000円(郵便物転送込・送料実費) |
| 高機能 | 月額8,000〜30,000円(会議室・秘書代行込み) |
Karigoは明確な料金体系で、コストと安心のバランスが取れたプランを提供しています。
よくある質問(FAQ)
-1024x535.jpg) バーチャルオフィスで登記を検討する方から寄せられる代表的な質問をまとめました。
バーチャルオフィスで登記を検討する方から寄せられる代表的な質問をまとめました。
バーチャルオフィスでの登記は違法ではないのか?
違法ではありません。商業登記法に基づき、バーチャルオフィス住所も本店所在地として認められています。
会社法第27条および商業登記法第48条では、法人は本店所在地を登記することが義務付けられていますが、必ずしも物理的な事務所である必要はありません。
郵便物の受取が可能で、法的書類を確実に受け取れる場所であれば、本店所在地として登記が可能です。
実際に、全国の法務局でバーチャルオフィスを利用した登記申請が日常的に受理されており、法的にも問題はありません。
郵便物や電話番号はどのように利用できますか?
Karigoでは、郵便物は各拠点で受取・保管され、希望に応じて即日・週1回・月1回転送などのスケジュールを選択できます。
写真通知サービスは一部拠点で対応しており、届いた郵便物をスマートフォンから確認可能です。
電話サービスは転送専用の共通電話番号や秘書代行サービスを利用できます。かかってきた電話を携帯電話や指定番号へ転送したり、スタッフが応対して伝言を受け取ることも可能です。
電話転送・秘書代行の料金は、プランにより月額1,100円〜3,300円程度が目安です。利用目的や業務量に応じて、必要なオプションを柔軟に組み合わせることができます。
契約期間や解約時の注意点は?
多くのバーチャルオフィスには最低契約期間が設定されています。
一般的な契約条件
☑最低利用期間:2ヶ月〜1年
☑短期利用時の違約金:残期間分の料金
☑解約予告期間:1ヶ月前までに通知
短期利用を想定している場合は、契約前に必ず確認が必要です。また、解約時には以下の手続きが必要になります。
解約前にすべきこと
☑新しい住所への本店移転登記
☑税務署・都道府県税事務所への届出
☑銀行・取引先への住所変更通知
☑郵便物の転送設定
解約後も郵便物転送(有料オプション)を一定期間継続できる拠点もあります。
同一住所で複数社が登記していると信用を落としますか?
同住所での多数登記自体は違法ではありませんが、取引先によっては懸念を持たれる可能性があります。
信用を落とさない工夫
☑会社Webサイトを充実させる
☑事業内容を詳しく記載
☑代表者プロフィールを公開
☑実績や取引先を掲載
☑問い合わせフォームを設置
事業実績を積極的にアピール
☑契約書や実績資料を準備
☑顧客の声やレビューを公開
厳格な審査基準の事業者を選ぶ
☑反社チェックが厳格な事業者なら、同住所の他社も信頼できる
実際には、IT・コンサル・EC事業など、オフィス不要な業種では、バーチャルオフィス利用は一般的になっており、適切な説明ができれば問題になることは少ないです。
バーチャルオフィスの住所でも税務署に届出できますか?
 はい、可能です。法人設立届出書や開業届にバーチャルオフィスの住所を記載して提出できます。
はい、可能です。法人設立届出書や開業届にバーチャルオフィスの住所を記載して提出できます。
税務署、都道府県税事務所、市町村役場のいずれもバーチャルオフィスの住所で届出を受け付けています。郵便物が確実に届く住所であれば問題ありません。
ただし、税務調査が入る場合には、実際の事業所(自宅など)での調査が行われることもあります。適切な帳簿管理と書類保管を行っていれば、特に問題は生じません。
登記後にバーチャルオフィスを解約するとどうなりますか?
登記住所を解約する場合は、速やかに本店移転登記が必要です。Karigoでは、移転先の選定や登記変更サポートも行っており、スムーズに手続きを進められます。
登記変更には登録免許税(管轄内3万円・管轄外6万円)と司法書士報酬(3〜8万円)がかかります。
まとめ|バーチャルオフィスで法人登記を成功させるために
今回の記事では、バーチャルオフィスでの法人登記の可否や手順、注意点について紹介しました。
・商業登記法に基づき、バーチャルオフィス住所でも合法的に登記できる
・自宅住所を公開せず、コストを抑えて一等地の住所を利用できる
・銀行口座開設や許認可業種では追加の準備が必要
以上のポイントを踏まえ、信頼できる運営事業者を選び、登記・融資・実務面のサポートが整った環境で起業を成功させましょう。
Karigoトップ – バーチャルオフィスならKarigo
※詳しくはkarigoの店舗一覧を確認してください。