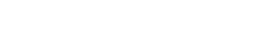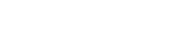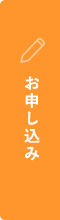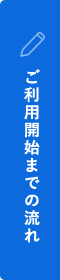2022年に電子帳簿保存法が改正され、データ保存の方法が変更となりました。
個人事業主の方も対応が必要になるため、しっかりと内容を把握しておかなければいけません。
そこで今回は、そもそも電子帳簿保存法とは何なのか、法改正によって何が変わり、どう対応すれば良いのか、といったことをご説明いたします。
 電子帳簿法とは、請求書や領収書など、税務にかかわる書類を電子データで保存できるように認める法律のことです。
これまでは、税務にかかわる書類は紙で保存しておかなければいけませんでしたが、この電子帳簿法が制定されたことによって、現在ではパソコン内の電子データで請求書や領収書を保存しておくことが可能です。
電子帳簿保存法では、データとして保存できる書類を3つの区分に分けています。
①電子帳簿保存
電子帳簿保存は、パソコンなどで作成した電子データを、紙にせずそのまま保存することです。会計ソフトで作成した請求書などが当てはまり、データを印刷する必要はありません。
②スキャナ保存
スキャナ保存は、紙で作成した書類を、画像データとして保存することです。
相手から紙の状態で受け取った請求書や領収書は、スキャンしてデータとして保存できます。
注意点として、スキャナに保存する際は、データにタイムスタンプをつけることが必要です。
③電子取引
電子取引は、データで受け取った取引情報を、そのままデータで保存することです。
取引先からメールで請求書や領収書を受け取った場合、紙に印刷する必要はなく、そのままデータとして保存できます。
電子帳簿法とは、請求書や領収書など、税務にかかわる書類を電子データで保存できるように認める法律のことです。
これまでは、税務にかかわる書類は紙で保存しておかなければいけませんでしたが、この電子帳簿法が制定されたことによって、現在ではパソコン内の電子データで請求書や領収書を保存しておくことが可能です。
電子帳簿保存法では、データとして保存できる書類を3つの区分に分けています。
①電子帳簿保存
電子帳簿保存は、パソコンなどで作成した電子データを、紙にせずそのまま保存することです。会計ソフトで作成した請求書などが当てはまり、データを印刷する必要はありません。
②スキャナ保存
スキャナ保存は、紙で作成した書類を、画像データとして保存することです。
相手から紙の状態で受け取った請求書や領収書は、スキャンしてデータとして保存できます。
注意点として、スキャナに保存する際は、データにタイムスタンプをつけることが必要です。
③電子取引
電子取引は、データで受け取った取引情報を、そのままデータで保存することです。
取引先からメールで請求書や領収書を受け取った場合、紙に印刷する必要はなく、そのままデータとして保存できます。
 2022年の1月に、テレワークやペーパーレス化の推進を目的として、電子帳簿保存法が改正されました。
これに伴って、これからは、③電子取引のデータは、電子データのままで保存しておくことが義務付けられます。
例えば、これまでは、メールで送られてきたデータやクレジットカードのWeb詳細などは、紙に印刷して保存しておくことも可能でした。
しかし、これからは、これらのデータは電子データとして保存しておかなければ、税務に関する書類として扱うことができなくなります。
ですが、紙への保存が厳しくなった反面、データの保存要項に関しては緩和されているため、これまで以上にかんたんにデータを保存することができます。
例えば、今までは③電子取引においては、タイムスタンプを付与しなければいけませんでした。
しかしこれからは、訂正や削除履歴が残るシステムに保存することで、タイムスタンプは不要になります。
また、税務署からのデータのダウンロードの求めがあった際、今までは日付や金額の範囲指定ができる検索の方法が必要でしたが、これらも不要になります。
2022年の1月に、テレワークやペーパーレス化の推進を目的として、電子帳簿保存法が改正されました。
これに伴って、これからは、③電子取引のデータは、電子データのままで保存しておくことが義務付けられます。
例えば、これまでは、メールで送られてきたデータやクレジットカードのWeb詳細などは、紙に印刷して保存しておくことも可能でした。
しかし、これからは、これらのデータは電子データとして保存しておかなければ、税務に関する書類として扱うことができなくなります。
ですが、紙への保存が厳しくなった反面、データの保存要項に関しては緩和されているため、これまで以上にかんたんにデータを保存することができます。
例えば、今までは③電子取引においては、タイムスタンプを付与しなければいけませんでした。
しかしこれからは、訂正や削除履歴が残るシステムに保存することで、タイムスタンプは不要になります。
また、税務署からのデータのダウンロードの求めがあった際、今までは日付や金額の範囲指定ができる検索の方法が必要でしたが、これらも不要になります。
1.電子帳簿法とは
 電子帳簿法とは、請求書や領収書など、税務にかかわる書類を電子データで保存できるように認める法律のことです。
これまでは、税務にかかわる書類は紙で保存しておかなければいけませんでしたが、この電子帳簿法が制定されたことによって、現在ではパソコン内の電子データで請求書や領収書を保存しておくことが可能です。
電子帳簿保存法では、データとして保存できる書類を3つの区分に分けています。
①電子帳簿保存
電子帳簿保存は、パソコンなどで作成した電子データを、紙にせずそのまま保存することです。会計ソフトで作成した請求書などが当てはまり、データを印刷する必要はありません。
②スキャナ保存
スキャナ保存は、紙で作成した書類を、画像データとして保存することです。
相手から紙の状態で受け取った請求書や領収書は、スキャンしてデータとして保存できます。
注意点として、スキャナに保存する際は、データにタイムスタンプをつけることが必要です。
③電子取引
電子取引は、データで受け取った取引情報を、そのままデータで保存することです。
取引先からメールで請求書や領収書を受け取った場合、紙に印刷する必要はなく、そのままデータとして保存できます。
電子帳簿法とは、請求書や領収書など、税務にかかわる書類を電子データで保存できるように認める法律のことです。
これまでは、税務にかかわる書類は紙で保存しておかなければいけませんでしたが、この電子帳簿法が制定されたことによって、現在ではパソコン内の電子データで請求書や領収書を保存しておくことが可能です。
電子帳簿保存法では、データとして保存できる書類を3つの区分に分けています。
①電子帳簿保存
電子帳簿保存は、パソコンなどで作成した電子データを、紙にせずそのまま保存することです。会計ソフトで作成した請求書などが当てはまり、データを印刷する必要はありません。
②スキャナ保存
スキャナ保存は、紙で作成した書類を、画像データとして保存することです。
相手から紙の状態で受け取った請求書や領収書は、スキャンしてデータとして保存できます。
注意点として、スキャナに保存する際は、データにタイムスタンプをつけることが必要です。
③電子取引
電子取引は、データで受け取った取引情報を、そのままデータで保存することです。
取引先からメールで請求書や領収書を受け取った場合、紙に印刷する必要はなく、そのままデータとして保存できます。
2.電子帳簿法は2022年の改正で何が変わった?
 2022年の1月に、テレワークやペーパーレス化の推進を目的として、電子帳簿保存法が改正されました。
これに伴って、これからは、③電子取引のデータは、電子データのままで保存しておくことが義務付けられます。
例えば、これまでは、メールで送られてきたデータやクレジットカードのWeb詳細などは、紙に印刷して保存しておくことも可能でした。
しかし、これからは、これらのデータは電子データとして保存しておかなければ、税務に関する書類として扱うことができなくなります。
ですが、紙への保存が厳しくなった反面、データの保存要項に関しては緩和されているため、これまで以上にかんたんにデータを保存することができます。
例えば、今までは③電子取引においては、タイムスタンプを付与しなければいけませんでした。
しかしこれからは、訂正や削除履歴が残るシステムに保存することで、タイムスタンプは不要になります。
また、税務署からのデータのダウンロードの求めがあった際、今までは日付や金額の範囲指定ができる検索の方法が必要でしたが、これらも不要になります。
2022年の1月に、テレワークやペーパーレス化の推進を目的として、電子帳簿保存法が改正されました。
これに伴って、これからは、③電子取引のデータは、電子データのままで保存しておくことが義務付けられます。
例えば、これまでは、メールで送られてきたデータやクレジットカードのWeb詳細などは、紙に印刷して保存しておくことも可能でした。
しかし、これからは、これらのデータは電子データとして保存しておかなければ、税務に関する書類として扱うことができなくなります。
ですが、紙への保存が厳しくなった反面、データの保存要項に関しては緩和されているため、これまで以上にかんたんにデータを保存することができます。
例えば、今までは③電子取引においては、タイムスタンプを付与しなければいけませんでした。
しかしこれからは、訂正や削除履歴が残るシステムに保存することで、タイムスタンプは不要になります。
また、税務署からのデータのダウンロードの求めがあった際、今までは日付や金額の範囲指定ができる検索の方法が必要でしたが、これらも不要になります。